過去問の具体的な使い方!演習から解き直しまで徹底解説!
大学受験において避けて通れないものが過去問演習。しかし、はじめの方は使い方がわからず困ることが多いと思います。そこで今回は「過去問の使い方の8つの手順」を解説していきます!
ここで質が変わる!?演習中にすべきこと3選
過去問は演習するとき、最大限本番と同じ状況にすることとすべての問題を解くようにすることを最大限意識していくべきです。
また後々解説しますが、過去問演習は解き直し段階が学力を伸ばす最大のチャンスであるため解き直し時を意識した演習が重要になってきます。
演習中にすべきこと①:時間を測れ
過去問演習は本番と同じように解くことが大事です。そのため時間は必ず測るようにしましょう。時間をはかる際はタイマーと時計の両方を使うことがおすすめです。
まず本番同様に時間制限を設けるために、タイマーを試験時間と同じ時間でセットしましょう。しかし本番はタイマーは見れないので演習中はタイマーは見えない位置において、時計で制限時間を確認する癖をつけるのがおすすめです。
演習中にすべきこと②:時間内に解けなかった問題も解ききる
過去問は実際に入試で出た問題であるため1問も無駄にしてはいけません。そのため時間内に解けなかった問題も解くようにすべきです。時間内に解けなかったからといって解かない問題をつくるのはもったいないです。
その際、解けなかった問題を解く目標時間を定めて解くようにしましょう。
時間内に解けなかった問題も目標時間を定めることによって、本番に近い形で解くことができるようになります。時間を意識することは過去問演習において重要なことなので常に意識するようにしましょう。
また、時間内に解けなかった問題は解き直しのときにわかるようにマークをつけておくと解き直しのときに便利ですよ。
演習中にすべきこと③:自信のない問題には印をつける
演習中にどうしてもわからなくて勘で解くことになる問題が出てくると思います。そのような問題はあっていたとしても絶対に解き直しのときに解説を見るべきです。たまたまあっていた問題を解き直ししないと本番で同じような問題が出たときに全く自信が持てないはずです。
たまたまあっていた問題も解き直しができるように、演習中に自信のない問題には印をつけるべきです!
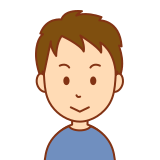
印をつけておくと、時間があまった際の見直しの時にも役立ちますよ
一番伸びる!おすすめ解き直し術の3つの手順
勉強全般においていえることですが、一番成績が伸びるタイミングは問題演習後の解き直しです。過去問演習も解き直しをいかにやるかで質が大きく変わってきます。
そこで僕が実際に使っていた解き直し術を3つの手順にわけて説明していきます!
解き直しのやり方①:解答を読んでまるつけをする
まずは正しくまるつけをしていきましょう。基本的なことですがここで採点を大きく間違えるとのちの手順に響きます。
間違えの内容に正しく採点しましょう
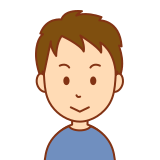
意外とまるつけは間違えやすいから慎重にいこう
解き直しのやり方②:間違えと自信のない部分の解説を読み込む
次に解説を読んで間違えた部分、自信がなかった部分を理解していきましょう。
この際に自分が解説のどの部分でつまずいたのか、なぜ間違えたのかを考えながら読み込んでいくようにしましょう。
英語の和訳を例にとると、間違えた原因には単語、熟語、文法、解釈、日本語力など様々な原因が考えられます。自分がつまずいたのはどの部分なのかをしっかり理解することで解き直しの質が大きく向上します。
解き直しのやり方③:間違えノートと分析ノートをつくる
過去問をやったうえで自分の学力を伸ばすためにノートを二種類作りましょう。
具体的には間違えノートと分析ノートをつくることがおすすめです。
まず間違えノートとは、自分の間違えた問題をまとめるノートです。間違えた問題を解説とセットでコピーしてノートにまとめて後で見返せるようにしましょう。
間違えた問題はくり返し解くことで習得できるので、ひとつのノートにまとめていつでも間違えを演習し直すことができるようにしましょう!
次に分析ノートについてです。分析ノートは問題の傾向と自分の弱点を記録していくノートです。ノートに書くことは自分で考えないとできない行為なので、書くことで勝手に志望校と自分の学力について分析できるようになります。分析ノートには①今回の演習で分かった志望校の傾向②今の自分の苦手な分野③これから苦手をつぶすためにやることの3つを書くことがおすすめです
さらに過去問演習の質を上げる?!2つの演習後にすべきこと
ここからは演習後にすべきことを2つに絞って話します。実際に成績を伸ばすためには、過去問を解いて得た情報を用いて学習をしていくことが重要です。
演習後にすべきこと①:苦手な単元を参考書で復習する
さきほど紹介した分析ノートにてこれから苦手をつぶすためにすることを考える項目を設けていました。これに沿いながら、自分のもっている参考書で苦手な分野を改めて確認すべきです。
このとき、周辺知識も含めて復習することがおすすめです。
苦手分野を網羅的に理解できるようになり、苦手の解消が早くなります。
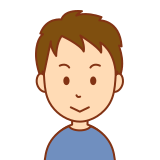
すこしめんどうくさいけど、参考書をしっかり確認しよう
演習後にすべきこと②:新しく参考書を買う
自分の持っている参考書では補いきれないような難易度の問題が過去問で出た場合はレベルをあげた参考書を買うようにしましょう。
いくら簡単な参考書を完璧にしたとしても、過去問が難しい場合は対応できない場合があります。過去問のレベルについていくためにもレベルをあげた参考書を購入する必要があるかを検討しましょう。
まとめ
今回は過去問演習のやり方の手順について解説していきました。
過去問は最高の教材です、だからこそ今回の記事を参考にしながらぜひ最高の質の過去問演習をしてくださいね。

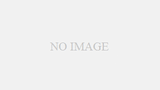

コメント